虫刺症(虫刺され)渋谷で虫刺されの治療なら|おおしま皮膚科【強いかゆみ・腫れにも対応】
虫刺症(虫刺され)とは

虫刺症(ちゅうししょう)は、いわゆる「虫刺され」のことで、蚊、ノミ、ダニ、ハチ、ムカデ、毛虫などに刺されたり、咬まれたり、体液や毒針毛に触れたりすることで生じる皮膚炎の総称です。
軽いかゆみや赤みから、強い腫れ、水ぶくれ、痛み、さらには感染症やアナフィラキシーといった全身反応を引き起こすこともあります。
特に小児やアレルギー体質の方は重症化しやすいため、適切な初期対応や治療が重要です。
虫刺症の原因となる虫の分類と特徴
吸血する虫
蚊、ブユ、ノミ、イエダニ、トコジラミ、マダニ
刺す虫
スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ、アリガタバチ
咬む虫
ムカデ、クモ、アオバアリガタハネカクシ
接触で皮膚炎を起こす虫
チャドクガ、ドクガ、イラガ
※また、「虫」ではありませんが、クラゲ、ヒトデ、魚類などの海生動物でも皮膚炎を起こすことがあります。
虫刺症の症状
即時型反応の症状
刺された直後〜数時間以内に発症。
かゆみ、赤み、じんましん、腫れ、痛みなど。多くは短時間で軽快。
遅延型反応の症状
刺されて数時間~数日後に発症。
ブツブツ(丘疹)、水ぶくれ、広範な腫れ。
数日~1週間続き、色素沈着を残すこともあります。
特に小児ではまぶたや耳が腫れ、眼が開かなくなる例もあります。
虫刺症の検査と診断
通常の虫刺されでは検査は行いませんが、以下のような場合は血液検査・抗体検査を実施します。
- ハチアレルギーの評価(RAST)
- ライム病、日本紅斑熱、ツツガムシ病などの感染症の鑑別
- IgE上昇(ガ、蚊、ゴキブリ、ヒョウヒダニ等への感作)
虫刺症の治療法
虫刺されの症状として代表的なものは、かゆみ・赤み・痛み・腫れ・水ぶくれです。
症状の程度や種類に応じて、以下のような治療やケアを行います。
自宅でできるケア
- 冷やす
かゆみ・腫れ・痛みの軽減に有効です。氷や保冷剤をタオルに包んで10~15分冷却しましょう。 - 掻かないよう注意する
掻き壊すと「とびひ」や色素沈着の原因になります。爪を短くする、ガーゼで覆うなどの工夫も有効です。 - 流水で洗い流す
虫の毒素や体液を取り除き、腫れや感染を防ぎます。毛虫やムカデ、クモに刺された場合に特に有効です。
外用治療
- ステロイド外用薬
炎症・腫れ・赤みに効果的です。強さや使用期間は症状に応じて医師が調整します。 - 抗ヒスタミン外用薬
かゆみの緩和に使用されます。 - 抗菌外用薬
掻き壊しや「とびひ」を伴う場合に使用します。
内服治療
- 抗ヒスタミン薬
かゆみが強い場合や広範囲にわたるアレルギー反応に対して使用します。 - ステロイド内服薬
炎症が強く、外用治療のみで改善しない場合に短期間使用します。 - 抗生物質
とびひや蜂窩織炎など、細菌感染が疑われる場合に使用します。 - テトラサイクリン系抗菌薬など
ライム病や日本紅斑熱などダニが媒介する感染症が疑われる場合に使用します。
虫刺症の重症化と合併症への対応
とびひ(伝染性膿痂疹)
掻き壊しによる細菌感染。水ぶくれやただれ。抗菌薬が必要。
蜂窩織炎
皮下深部への感染。強い腫れ、発熱、切開が必要なことも。
ライム病
マダニ媒介の感染症。紅斑、関節痛など。早期の抗菌薬投与が重要。
アナフィラキシー
重篤なアレルギー反応。呼吸困難、意識障害、血圧低下など。エピペン+救急対応が必要。
虫刺症の予防方法
- 長袖・長ズボン・手袋・帽子で肌の露出を避ける
- 暗い色の服を避けて明るい服を着る
- 虫よけスプレー(ディート/イカリジン)の活用
- 網戸や蚊帳の使用、ネズミやダニの駆除
- 洗濯物を屋外に干す際は毒針毛の季節に注意
注意すべき虫の特徴と注意点
| 虫の種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| ハチ類 | 即時の激しい痛み・腫れ | アナフィラキシーに注意。エピペン対象。 |
| 毛虫 | 毒針毛が風や衣類に付着 | 洗い流す、こすらない |
| アオバアリガタハネカクシ | 線状皮膚炎 | 潰さずに水で洗うこと |
| トコジラミ | 夜間に吸血 | 駆除が困難、長引くことも |
| シラミ類 | 頭や陰部に寄生、卵を産む | 家族全員で治療が必要 |
| マダニ | 皮膚に長時間吸着し感染症を媒介 | 無理に取らず皮膚ごと切除 |
アナフィラキシーと緊急対応
ハチ刺されなどで以下の症状があれば、すぐに救急車を呼んでください。
- 息苦しさ、喘鳴
- 全身のじんましん
- 吐き気、腹痛、意識の低下
- 顔面蒼白、血圧低下 ※過去に反応が出たことのある方は、アドレナリン自己注射薬(エピペン)の処方をご相談ください。
よくあるご質問(FAQ)
- 虫刺されで腫れたときの対処方法は?
- まずは刺された部分を水道水で洗い、冷やすのが基本です。
氷や保冷剤をタオルで包み、10~15分ほど冷却することで炎症やかゆみが軽減します。
腫れが強い場合は、ステロイド外用薬を使用し、症状が改善しない場合は早めに皮膚科を受診してください。
掻きむしりは悪化や感染の原因になるため避けましょう。 - 虫に刺された場合、病院へ行くべき症状はありますか?
- 赤みや腫れが広がる、水ぶくれや強いかゆみ、発熱を伴う場合は、早めに皮膚科を受診してください。
- 刺された記憶がなくても、虫刺されの可能性はありますか?
- ダニや毛虫などは無自覚で皮膚炎を起こすことがあります。腫れやかゆみが数日続く場合は受診をおすすめします。
- 市販の虫刺され薬で治らないときはどうすれば?
- 市販薬で効果がなければ、ステロイド外用薬や抗アレルギー薬など、適切な治療を受けるため皮膚科を受診してください。
- 病院にいく前にやることはある?
- 毛虫の毒針毛に触れた場合は、初期であれば粘着テープで毒針毛を除去し、洗浄してください。
ムカデ、クモによる刺咬直後の疼痛には水道水で洗浄後、アイスノン等でしっかり冷やしておいてください。
ミツバチに刺された後に毒嚢が突き刺さったまま残ることがあり、その場合は直ちに取り除いてください。
そのままにしておくと毒嚢内の毒がさらに数秒の間注入されるといわれています。
また、刺さった毒針を残しておくと感染の原因にもなります。
刺し傷を水道水で洗い流し、氷で冷やすことによって痛みは和らぎます。
アンモニアを塗ると毒の酸性を中和し痛みが和らぐといった俗説もありますが、全く根拠がないので行わないでください。 - 虫刺されを繰り返す子どもの予防法は?
- 長袖・長ズボンの着用など、野外では肌を露出しないようにしましょう。
虫よけスプレーも有効ですが、子どもへの使用には制限があります。
虫よけスプレーの主成分であるディートは副作用の少ない薬剤ですが、6 カ月未満の乳児には使用しない、6カ月以上2 歳未満は1 日1回、2 歳以上12 歳未満は1 日1~3 回の使用にとどめ、顔には使用しないなどの注意が必要です。 - ハチに刺されて具合が悪くなった場合どうしたらいい?
- 息苦しさやじんましん、意識障害がある場合は、安静にして救急車を呼んでください。ハチに刺されてショック状態になったことのある人はアドレナリン自己注射キット(エピペン)の携帯をお勧めします。当院でも処方しておりますのでお気軽にご相談ください。
| <<< | 2026年02月 | >>> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 営業日 | 休診日 | |||||
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町25-18
NT渋谷ビル3F
TEL 03-3770-3388
FAX 03-3770-3385

|
|

|

|
|
|

|
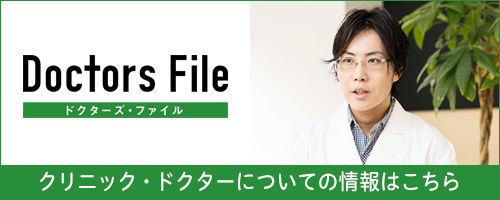
|
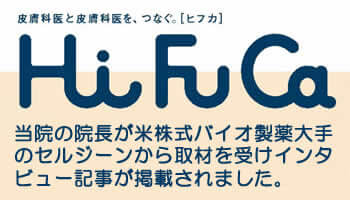
|
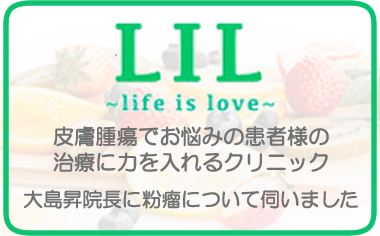
|
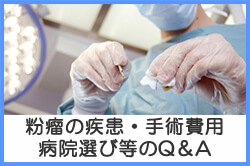
|

|
|
こちらから

